藪をかき分け、山に入る。
足元の春は芽吹きつつも、木々たちのほとんどはまだ蕾のままだ。雲一つない青空を抜けて、まだ林とも呼べぬ山肌に陽が差し込む。
目の前に、高さ5m以上もの大岩がある。岩の上には、太く株立ちした木が、堂々と生えている。大岩を迂回するかのように、斜面を小さな川が段々と流れ落ちている。
大岩を横に、腰を下ろす。数十m上には林道が走っているが、殆ど車が通ることは無く、位置関係で路上の車からこちらが見えることも無い。
瞑想するかのように、目は閉じずに、静かに自然との同化を試みる。川の音、小鳥のさえずり、杉林が風に揺れる音が聞こえる。
最初に現れたのはカナヘビだった(蛇ではなく、トカゲっぽいやつだ)。右手の少し横をしゅるしゅると向こうへと歩いていく。
左上方にある水平な枝では、黄色い小鳥が断続的に歌っている。
斜面の上の方から、特徴的な色合いの鳥が颯爽と現れ、対岸に着地する。カケスだ。せわしなく小さく跳びまわった後、向こうの林へ消えて行った。
自然を感じるコツの一つは、静かにすることだ。
人間を警戒する動物は多く、人間の存在が目立っていては、自然は真の姿を見せてくれない。木化け、石化けと言う言葉が猟師界隈にはあるが、木や石に化けるかのように、そっとそこに佇むことで、森の住人たちに邂逅する確率は高まる。
しばらくそんな風に静かに佇んでは、訪れる動物たちを愛でつつ、風を感じ、水の音を聴き、自然を感じていた。
刹那。ぬっと、右前方、斜面の切れ端から大きな影が現れた。
刺すような警戒感が、穏やかな心地を砕く。
1秒も経たず、安堵した。カモシカだ。
おそらくこちらに気付いてないのだろう。のっそりと対岸の斜面を音もたてず歩いていく。距離は20mくらいだろうか。
これまで数十回とカモシカを見たことはある(近づきすぎて威嚇されたこともある)が、これほど近くで悠々としている姿は記憶にない。
自然なカモシカの姿を、落ち着きと興奮が入り混じった心地で観察する。時折り立ち止まっては木々の芽を食みつつ、ゆっくりと斜面を水平にトラバースしていく。
暫くして、車の音が聞こえてきた。上の林道を、ほどなく車が通るだろう。
面白い、と思った。カモシカが今いるのは、ちょうどその林道の真下の斜面だ。道からの距離は、10mもないだろう。
どんな反応をするのだろうか?と興味が湧く。ふと頭を過ぎったのが、いつもカモシカの姿だ。山で出会うと、こちらをじっと見つめて停止する、あの姿。
正にこの林道で車に乗っている時にも何度もカモシカに会ったことがあるが、例外なく、彼らは暫くじっとこっちを見つめ、やがて去っていった。
エンジン音が近づいて来る。いよいよ真上を車が通る。さぁ、どんな反応を見せるのか?—
—何も無かった。頭上を通り過ぎていく車など意にも介さず、悠々と木の芽を食みつつ歩いていく。
衝撃的だった。なるほど、彼らはこうやって生きていたのか。
人間と出会ってしまえば流石に警戒態勢に入るが、そこを車が通るだけでは、人間が頭上を通っていくだけでは、問題が無いことを彼らはきっと知っているのだろう。
人間がたまにそこを通ることを当たり前として、自然の中に生きている。警戒しつつ、さりとて警戒しすぎずに。
勿論、これはカモシカが天然記念物と言う守られた存在であることも関係あるだろう。経験的には、狩猟対象獣のイノシシより(痕跡は周りに嫌ほどある)も、天然記念物のカモシカに出会う確率の方がずっと高い。
そんな風に自分が無暗に襲われない存在であることを感じ取っているのかもしれないが、やはり、その有様に一種の衝撃を受けざるを得なかった。
どこか、人間への排他的意識。そんなものを、動物たちは身をもって表すのだろうと思っていたし、これまでの出会いの中でも、そんな風に感じていた。
しかし、少なくとも、このカモシカの行動は、そうではなかった。頭上の人間の存在を、当然のノイズとして受け取ったのではないだろうか。
一方で、それも当然かもしれないとの思いも沸いてきた。
カモシカの寿命(高々15年程度)を考えると、きっとこの林道は、このカモシカが生まれた時から在ったはずだ。生まれた時から当たり前に存在する林道と人間の気配に、順応しないはずがない。
これは至極人間勝手な見方だが、彼らは彼らなりのやり方で、人間との共生を実践しているのかもしれない。
暫くそんな風に考えているうちに、カモシカは大岩の陰に隠れて見えなくなってしまった。
カモシカはいなくなったが、思考は続いた。
寿命を考えると、カモシカにとって、林道が走り度々人間がやってくる今の山の状態は、もはや当然であり“自然”なのであろう。
では、岩や、木はどうか。彼らに意思があると思い込んでる訳ではないが、その霊性みたいなものを仮定した場合、長く生きる彼らは、この現状をどう思っているのだろう?
人間がこれほどまでに音を立て山に入り込むことが無かった時代より存在するであろう彼らは、現代の自然に侵入する人間を、どんな風に見ているのだろうか?
そんな解り様もない問いの中に暫く漂いつつ、ふと先ほどのカモシカの在り方に意識が戻る。
そしてそんな姿を頭の中で反駁しつつ、忘れていた当たり前ことを思い出した。
「自然って、誰のものでもないんだよな、きっと。」
山地にも所有権があり、どこの土地が誰のものかというのは、決められている。
自分が山で遊ぶ時も、そういうことはそれなりに気にしていた。ここは市の管轄で、どうのこうの。ここまでは自分の土地なので、ここの竹は切っていい、だの。
しかしそれは、人間が、人間社会という限定的な世界の中で設定した虚構に過ぎない。そんなこと、動物たちは知らないし、関係ない。人間が、身内だけで勝手に決めただけのことだ。
人間社会で生きていく以上、その虚構を共同主観として受け入れる必要がある。
しかし、それは一種の幻想に過ぎないのだ。
自然というのは、ただそこにあって、誰のものでもない。
本来的な性質と、円滑に事を行うために設定されたルールがもたらした常識を、いつの間にか混同してしまっていた。
そんなことを自然に気付かされた、ひとときであった。
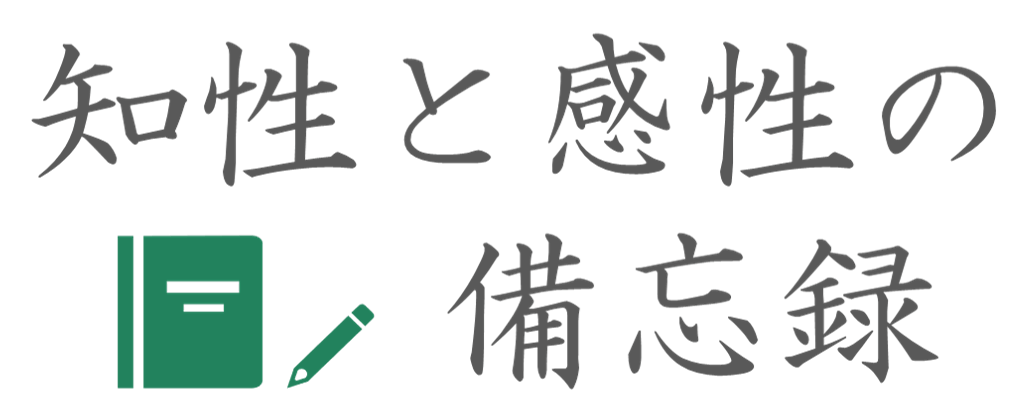


コメント